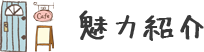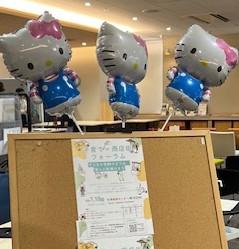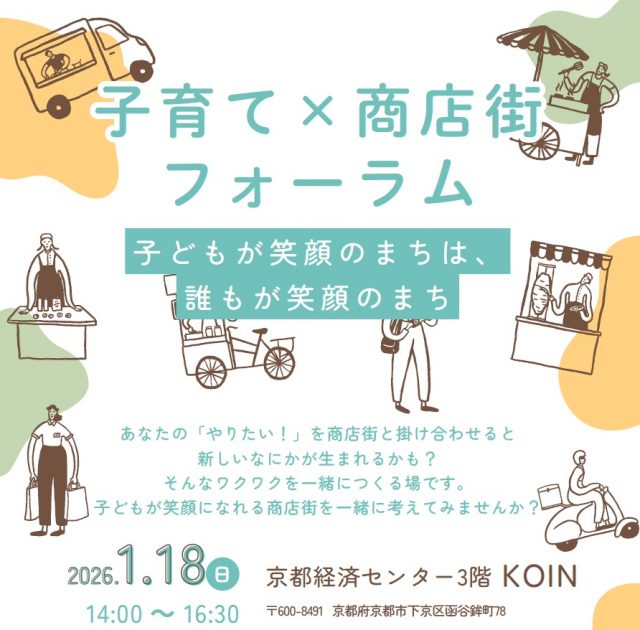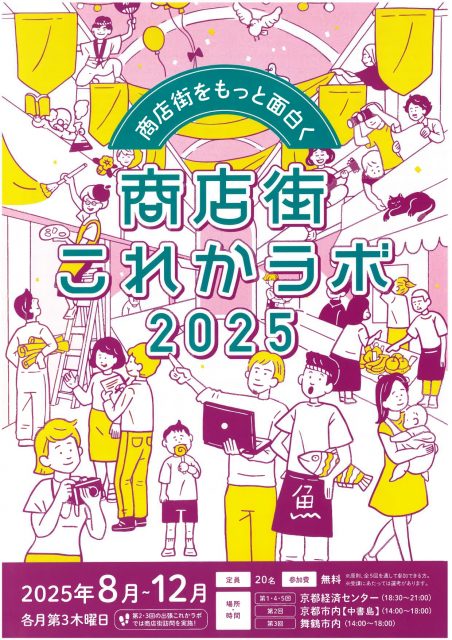久保敦史さん:1984年生まれ。神戸出身。立命館大学産業社会学部卒。2008年に乾ゼミのフィールドワークで出町地区のまちづくり団体でまち倶楽部に参画したことをきっかけに地域に関わり始める。「教室にいるよりも、外に出る」という方針のゼミだったこともあり、積極的に地域住民とまちづくりに関わる。大学卒業後は、京都 と東京で様々な職を経験した後、学生時代からずっと関わりのあった出町地区で縁がありワインバー出町ランプを開業。3ヶ月前に店舗を移転し、来期で5年目に突入。
でまちになじむ
 久保さんが商店街を含めた「出町」という地域に関わりだしたのは2008年のこと。大学のゼミで出町班というグループに所属し、「でまち倶楽部」という任意のまちづくり団体と一緒に地域住民と関わりながらフィールドワークをしていたことがきっかけでした。その際、出町地域のキーパーソンである喫茶YAOMONの店主・佐々木さんと、当時京都工芸繊維大学(現在、福知山公立大学)の谷口先生と出会います。
久保さんが商店街を含めた「出町」という地域に関わりだしたのは2008年のこと。大学のゼミで出町班というグループに所属し、「でまち倶楽部」という任意のまちづくり団体と一緒に地域住民と関わりながらフィールドワークをしていたことがきっかけでした。その際、出町地域のキーパーソンである喫茶YAOMONの店主・佐々木さんと、当時京都工芸繊維大学(現在、福知山公立大学)の谷口先生と出会います。
久保さんが出町に関わりだした頃は、それまで数十年活発に行われてきた出町のまちづくり活動が、担い手不足や様々な要因によりややマンネリ気味だった時期でもありました。ワンルームマンションが増えて若者の顔が見えにくい時代。
そんな中、「まちに新しく来た人たちと地域の人たちが顔なじみになってもらいたい!」と久保さんたち出町班はまち歩きイベントでまちになじむを企画します。地域住人や商店主、さらには地域の高校生まで協力してもらった企画は現在も引き継がれ、今年でなんと12回目。(現在は、同志社大学の新川ゼミが続けています。)他にも子どもたちを外で思いっきり遊ばせたいと鴨川に30人ほど集めて水鉄砲をするイベントもあったそう。実際に蓋を開けてみると、大人の方が盛り上がってしまったのだとか。
「地域」と密接に関わった学生時代
 そんな出町の活動の中で、特に印象に残るのは飲み会。佐々木さんが営まれている喫茶YAOMONにて、月に1回「でまちサロン」という交流会があります。そこは、商店街でも地域の学区でもなく、そこの地域を好きな人がざっくばらんと集まって話せる場。毎週のように新しい顔ぶれが集まり、大学の先生や地域の人々と議論を交わしていたのだそう。
そんな出町の活動の中で、特に印象に残るのは飲み会。佐々木さんが営まれている喫茶YAOMONにて、月に1回「でまちサロン」という交流会があります。そこは、商店街でも地域の学区でもなく、そこの地域を好きな人がざっくばらんと集まって話せる場。毎週のように新しい顔ぶれが集まり、大学の先生や地域の人々と議論を交わしていたのだそう。
勢いがあり、前のめりな20代前半。いい意味で喧嘩ができる関係と言うのでしょうか。
”若者が投げかけたことに対して、大人がちゃんと返してくれた”と久保さんはおっしゃいます。そんなところからも徐々に信頼関係が生まれていき、そうやって関わっていくうちに、商店街の方々にも顔を覚えてもらうことができました。
京都に戻り、店を開く

▲出町ランプ開業の地。3坪の極小空間でしたがここで生まれた繋がりは数知れず。|写真提供:久保さん
大学卒業後、京都の会社に就職。半年間で貯めたお金を手に海外を放浪。帰国後、京都や東京で様々な職を経て27歳で再び京都へ。「何しよっかなぁ」とぶらぶら商店街を歩いていると、商店街の馴染みのおっちゃんに「自分の店でもやったらええんちゃう?ほら、あの角んとこ空いてるやん。」と提案されます。
そして2012年、出町ランプが誕生しました。「それまでの経験が活きる自然な流れでの開業だった。無知やったからできたのかも」と久保さんは当時を振り返ります。「やっぱり出町に縁があるんやなぁ」と。この頃にこれまでの経験が全部つながってきたのだとか。学生時代に関わった出町、歩いてきたヨーロッパの街並みや料理、ワイン。
実は、元々大家さんとも顔馴染みで「君やったら」と店舗を借りられることに。以前から店内を見ていて内装の改修イメージがついていたことと、フィレンツェのアルノ川の情景が鴨川に似てると感じていたことが相俟って出店に踏み切れたのだとか。
今、肌で感じる「出町」

▲移転後の出町ランプ店内|写真提供:久保さん
京都に帰ってきた当初はあの頃に比べて少し、パワーが低下しているような空気感。仲間が多かった4年前の「京都」はここにはなく、どこかまちが硬直してしまったような気配。何をするにしても、手をあげた人がやらざるを得ない状況。学生の出入りも少なくなり、でまちサロンのメンバーも固定化されつつありました。
そんな時にまた、若者が集まるようになってきます。出町にゆかりのある同年代の数人が、本格的に出町で活動を始めたのがきっかけでした。それが今、出町ファンの集まる団体でまちクラバーの結成へと繋がっていきます。2015年に正式に発足したこの団体のキーワードは”ゆるく、つながる”
現在、でまち倶楽部とも協力して人が集ってつながるイベントを開催しています。
「問題のないまち」だからこそ

▲移転後の出町ランプ外観|写真提供:久保さん
出町はずっと「問題のないまち」と言われています。今はどうにか維持できているものの、高齢化・後継者問題等必ずやってくる課題にどう対処していくのか。実際に、この1年間で出町商店街の組合数もおよそ1割減。変化が必要な時期に差し掛かったのかもしれません。
「でまちになじむ」や「でまちサロン」など1つの場所をみんなで創ることを通してまちに対して愛着がわくことを、身を持って体感していた久保さん。かつて、でまちサロンで地域の方々と議論を交わした際に、久保さんが意見を言うと、悲しそうに「お前は住んだりしてへんもんな〜」と返されて悔しい思いをしたことも。この時、「いつか出町に住めたらなぁ」と思ったのだそう。
これまでの人のつながりや経験、そして長年の想いから生まれた出町ランプ。ここでお店を営むことが久保さんにとっての「まちづくり活動」であり、ここからまた新たなコミュニティが広がっていきます。
みんなの見識が1%変わるということ
 実際に店を始めてみると、「ものの見方が変わってきた」と久保さんはおっしゃいます。学生の頃とはまた少し違った角度から出町と関わってみて、初めて見えてきたこともあるそう。
実際に店を始めてみると、「ものの見方が変わってきた」と久保さんはおっしゃいます。学生の頃とはまた少し違った角度から出町と関わってみて、初めて見えてきたこともあるそう。
久保さんは移転を考えた時、先に面白そうな物件を探すことから始められました。そこで何ができるかを考えるタイプで、あるものを活かすことにワクワクするのだとか。
ここにあるものが見えているからこそ、ここにないものを作れるのかもしれません。
今は時々、出町ランプの3階で常連のお客さんたちとイベントも開催しています。寄席の会や日本酒研究の会など、ジャンルは様々。そうして、久保さんを通して出町と関わる人が緩やかに増えていきます。
地域や商店街の「活性化」の答えは1つではなく、「どうなったら良いのか」という問いかけは幸福論に近い、と久保さんはおっしゃいます。
“まずはいろんな立場の人々が意見を交換できる場で、たとえ衝突する事があっても、それぞれに理解しあえたり気づきを得たり、顔を合わせて本音に耳を傾け合うこと。“
その結果、相互理解が少しずつでも増すことによって、まちも変わっていくのではないかと。
近所の不動産屋で働いている同じ乾ゼミ出町班出身の友人が、「商店街活性担当」をしているのもおもしろいですよね。